公開日:
更新日:
創業者インタビュー:日本におけるテクノロジー起業家精神 – パート2
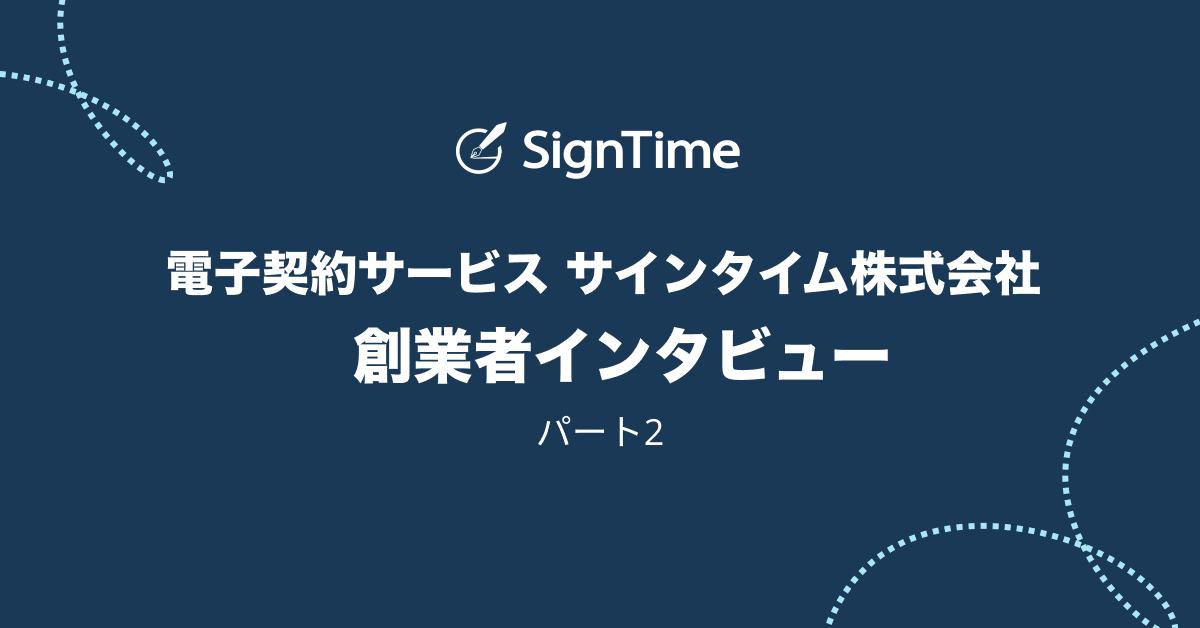
今回より、サインタイムは、テクノロジー業界、イノベーション、スタートアップ文化、そして日本におけるテクノロジービジネスの成長に関する様々なテーマについてのブログシリーズを展開します。シリーズの最初は、弊社CEO兼共同創業者であるジム・ワイザーとの「創業者紹介」インタビューからスタートしました。今回は、その第2部です。もし第1部をお見逃しの方は、こちらでご覧いただけます。
日本での規制上のハードルは難しいと感じますか?
規制の課題は、何をやっているかによります。サインタイムが電子契約に関わる法的な要素があるため、アメリカと比べると難しいですが、EUと比べると同程度です。
日本には「何か新しいことをする際には、許可が必要」という規制が多くあります。そのため、政府の手続きでフロッピーディスクやファックスが必要になることもあります。もちろん、現在の政府はその技術を積極的に選んだわけではありませんが、規制が制定または改定された当時はそれが最先端技術だったのです。アメリカではデフォルトが「許可されている」ですが、日本では「許可されていない」がデフォルトという状況です。
アメリカでのビジネス経験は日本に来る前にどれくらいありましたか?
ほとんどありません。私のビジネスキャリアはすべて日本でのものです。
日本で成功するビジネスを構築するためのステップは何ですか?
私たち(サインタイム)は、最初の本格的な提案に対して、法人を設立せずに入札を行いました。というのも、私もビジネスパートナーも既に法人を持っていたため、それを活用してビジネスユニットとして活動したのです。機会があるかどうか分からないうちに、弁護士や会計士にお金をかける必要はないと判断しました。その提案の後、私たちはビジネスとして成立する確信を得たので、プレシード資金調達の一環として法人化しました。
その最初の取引はどうなりましたか?契約を獲得しましたか?
いいえ、落札はしませんでしたが、それでも法人化を進めました。私のB2Bセールスの経験では、最初の取引で勝つことはほとんどありません。なぜなら、顧客が何を重視しているかを十分に理解できていないからです。2回目も勝ったことはありませんが、3回目になるとかなりの勝算があると考えています。そして、10回目までに契約を獲得できない場合、市場に対する理解が間違っているか、私たちがその市場に適していないということです。サインタイムに関しては、日本市場では電子契約の普及率が非常に低いため、長期的なチャンスは非常に大きいと考えています。
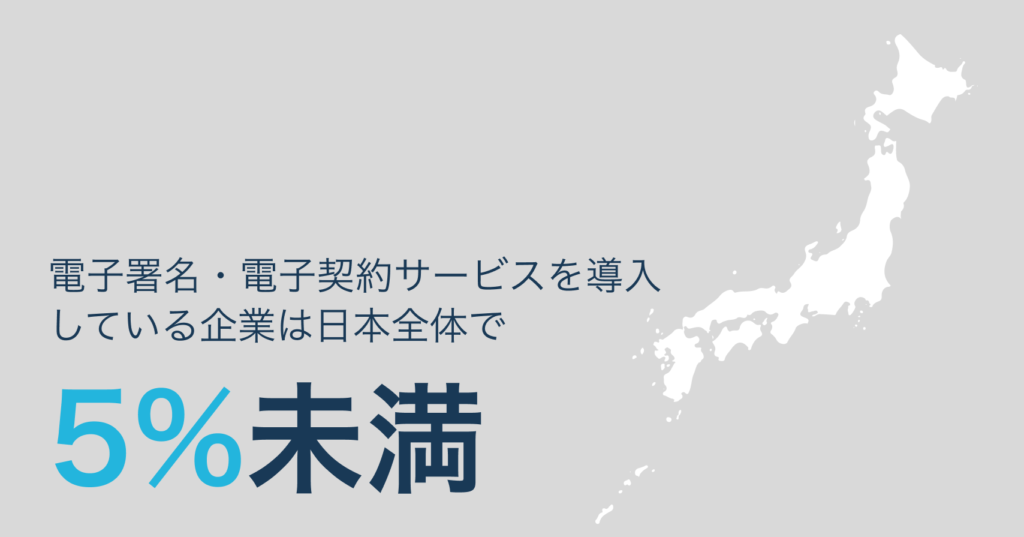
サインタイムの法人化後、次の発展段階でのステップは何でしたか?
採用です。その時点では、私たちは非常に忙しく、人員が不足していました。会社はまだ理論上の段階で、私は最初の従業員でした。高品質なチームを採用し、構築していく必要がありました。
これまでにスタートアップでの経験から、何か失敗談や教訓がありますか?
そうですね。一つ言えるのは、契約は基本的に執行が難しいということです。契約は、双方が合意に至った内容を思い出すためのものでしかありません。もし訴訟に至るようであれば、特に小規模で迅速に動くビジネスにおいては、すでに負けているようなものです。
その他、初期の採用に関しての失敗や教訓はありますか?
以前、潜在能力よりも過去の経験を重視して採用したことが何度かありましたが、うまくいきませんでした。その当時、スタートアップに参加するリスクを取れる人は、往々にして他に選択肢がない人でした。結果として、そうした人々はトップパフォーマーではないことが多かったのです。
この傾向は現在少し変わってきましたが、40代前半から50代前半にかけての稼ぎがキャリア全体の収入に大きく影響する日本の労働市場では、特にこの傾向が強く見られます。これは世界中どこでもある程度真実ですが、日本では特に顕著です。
その稼ぎの潜在力は、スタートアップで経験豊富なチームメンバーを雇う際に障害となることがあります。キャリアの終わりに差し掛かってスタートアップで働きたいという人もいるかもしれませんが、そうした人をアドバイザー以外の役割で活用できたことはありません。しかし、アドバイザーは場合によっては有効です。重要なのは、その人をどのような役割に位置付けるのかをお互いに理解することです。彼らにアドバイスを求めるのか、機会へのドアを開けてもらうのか、それとも別の何かを期待しているのかを明確にする必要があります。
初めて創業する人がよく犯す誤りの一つは、初期の従業員の動機が自分と同じだと考えることです。
創業者として、「私たちはこれを成し遂げるんだ、私たちでこれを築くんだ」と強く感じていました。しかし、従業員にとってはそれは仕事であり、創業者と従業員の間には大きなギャップがあります。確かに、彼らはリスクを取ってその仕事を選んだかもしれませんし、あなたを信じて参加したのかもしれませんが、それは全く別のことです。それに気付くまでに数年かかりました。
サインタイムの法人化後、最初の採用段階を経てビジネスをどのように構築しましたか?
テクノロジー業界、そしておそらく多くのビジネスにおいて、特に日本の流通の重要性が過小評価されがちです。多くの企業が、日本以外では直接販売を行っているにもかかわらず、日本市場においては顧客とのチャンネルがベンダー(供給者)によって厳しく管理されており、そのためベンダーロック(特定のベンダーに縛られる状況)が非常に強い傾向があります。
これは他の国でも同様ですが、アメリカでは社内に独立した機能が存在し、技術面で「これをやるべきだ」という意見が出ることが多いです。ですから、顧客基盤の構築には時間がかかると覚悟しておくべきです。特に日本は保守的で、関係性を重視する国なので、顧客基盤の構築に時間がかかります。
さらに、特にテクノロジー業界では、日本市場に進出して1年で撤退してしまう企業も多く、外国企業として認識されることが困難になることがあります。ここで重要なことは二つあります。一つは、市場を十分に理解せずに進出して撤退する企業が多いということ、もう一つは、日本企業の意思決定者のほとんどが、成長ではなくコスト管理で成功しているということです。
日本の人口減少を考えると、消費者も減少することになります。特に私と同世代のシニアマネージャーたちは、キャリアの大半を人口減少という逆風の中で過ごしてきました。そのため、彼らはコスト削減で成功を収めてきました。これは他の先進国や成長市場ではあまり見られないことです。
そのため、日本でビジネスを始めるのは難しいように思われますが、実際どうですか?
だからといって、日本で成功している外国人がいないわけではありません。非常に成功を収めた外国人企業家も多くいます。例えば、あまり知られていないかもしれませんが、Bill Tottenという起業家がいます。彼をご存知ですか?
Billは60年代後半から70年代初頭にIBMかどこかにいて、その時代のコンピュータ製品を販売する会社を立ち上げたいと考えました。彼が1972年に創業した会社は、株式会社アシスト(KK Assist)です。
それで、よく「自分は〇〇を初めてやる人かもしれない」と思っている人たちに、いや、あなたは初めてじゃないですよ、と私は言います。最近ではそうかもしれませんが、過去のことを知らないだけなんです。
そして、食品業界ではMrs. Fieldsのクッキーを扱っていたJoe Dunkelという人物もいます。彼はすぐに日本で流通の仕組みを整えました。このように成功した例は他にもたくさんあります。どうやって成功したのか?市場適応もあれば、ただうまくいったものもあります。
ある起業家たちが指摘するポイントとして、製品や製造よりもサービスでビジネスを始める方が簡単だと言います。なぜなら、ただそれをやるだけだからです。製品は設計、施設、在庫などに先行投資が必要です。それはどこでも同じではありませんか?
ええ、その通りです。だからこそ、コンサルタントが無数にいる理由なんです。
実際、私が2社目の会社を立ち上げた時、コンサルティングをやっていると人々に言ったところ、名刺を渡すと『ああ、失業しちゃったんですね』と言われました。本当に冗談じゃなくて。
私としては、いや、これは法人だし、実際にビジネスとしてやっているんですよ、と思っていたんですが、彼らは「そうですね、そう言うなら」と返してきました。これは2001年のドットコムバブル崩壊直後のことでした。2008年の世界金融危機の後も、多くの人々がコンサルタントをしながら仕事を探していましたが、私はその時点でその点を理解していませんでした。
そのため、このコメントは非常に正しいのですが、スケールするには限界があります。私が考えているのは、あなたがエンタープライズを築こうとしているのか、それともライフスタイルビジネスを築こうとしているのかということです。
エンタープライズビジネスの場合、創業者がいなくなってもビジネスは存続します。成長はどうなるかわかりませんが、少なくともビジネス自体は続きます。一方で、コンサルティング会社のようなビジネスでは、従業員はそれを楽しみながら仕事をし、数年後には社内で稼いでいた額よりも多くの収入を得ることができる場合が多いです。
1年目はまさに砂漠で迷っているようなものでした。食べ物も水も何もない状態でしたが、2年目の終わり頃には少なくともモーセを見つけました。まだ「乳と蜜の流れる地」ではありませんが、少なくともマナと水は手に入れました。コンサルティングビジネスでは、何もない状態から生活費を賄える状態に到達するのは可能です。
私たちは契約を「家賃の何ヶ月分か」という基準で評価していました。たとえば、家賃が月10万円だったとすると、「これは10ヶ月分の家賃に相当する契約だな」と考えていました。
その後、少数の従業員を雇いましたが、それらのコストは比較的小さかったです。エンタープライズビジネスを運営し始めた時、データセンターのインフラ、カスタマーサポートチーム、エンジニアリングチーム、セールスチームを揃えていました。
自分の貯蓄で従業員の給与をまかなえなくなった時点で、ビジネスがある程度の規模に達したことを感じました。これは、小さなビジネスを運営している人やエンタープライズを築こうとしている人なら誰でも経験することです。顧客が支払いを遅らせても、従業員には家賃を払う義務があるので、私たちは給与を支払わなければならないのです。起業家たちと話をしていると、この話題がよく出てきます。とてもよくあることです。
このインタビューの第3部もまもなく公開されますので、ぜひお楽しみにしていてください。ジムに質問したいトピックがあれば、ぜひご連絡ください!
